
公正証書遺言にすれば、形式不備も保管の心配もなくなるって本当?
はい、その通りです!相続専門の行政書士が、公正証書遺言の作り方から流れまで説明させていただきます。
公正証書遺言とは

公正証書遺言については、民法969条に定められています。
簡単に言いますと、公正証書遺言は公証人役場へ行き遺言者、公証人、証人2人以上が集まり遺言者の想いを残す遺言方式です。
以下、民法969条
公正証書遺言
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言のメリットはデメリットは
公正証書遺言の最大のメリットは、遺言書の内容にミスが発生しない。これに尽きると思います。
公証役場へいって、「自分の財産をこうしたい」と公証人へ告げ、公証人があなたの想いに沿った遺言書を作成してくれます。
公証人は法律の専門家。専門家が作るのですから、形式不備ということは、まずありえません。
その他のメリットしては、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるので、遺言書か紛失したり内容が変更される恐れがなくなります。
また、実際に相続が発生した場合に、専門家が作成したものなので、遺言の内容が不明瞭でわからないとうトラブルも抑止できます。
デメリットとしては、公証人役場に公正証書遺言を依頼する場合費用がかかるといったところでしょうか。
費用については、後述します。
どこの公証役場に頼めばいいのか

原則どこの公証人役場でも構いません。全国に約300か所あります。
ただ、公証役場とのやりとりなどを考えるとご自宅の近くの公証人役場を選ばれた方がいいと思います。
公正証書遺言の証人とは
民法969条に定められているように、「公正証書遺言」を作成する場合、証人が二人必要となります。
それでは、証人は身近な配偶者や子どもに頼めば大丈夫・・・
と思いますが、実は配偶者やお子さんは証人にはなれないんですね。
証人になれない者として、
- 未成年
- 推定相続人(遺言者が亡くなった後に相続人となる人)
- 推定族人の配偶者
- 推定相続人の直系血族(親や子、孫)
- 受遺者(遺言で財産もらう人)
- 受遺者の配偶者、直系血族
などがあげれます。
なので、配偶者やお子さんは推定相続人になりますので、証人にはなれないんです。
逆に、上記に該当しない者、相続にまったく関係にない第三者を証人とすれば問題ないということになりますね。
しかし、そんなことを気軽に頼める第三者なんていない、知り合いに頼むのは内容がばれそうで嫌だというかたも多くいらっしゃいます。
そんな時は、公証役場で証人を依頼すれば証人を用意してくれるところもあります。費用は公証役場によりまちまちですが、だいたい5千円~1万円程度と考えておくといいでしょう。
公正証書遺言に必要な書類

公正証書遺言を作成するためには、多くの書類が必要となります。
たとえば、
- 遺言者本人の本人確認の書類として実印と3カ月以内の印鑑証明書。
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本全部事項証明書
- 財産に不動産があればその登記簿謄本と固定資産評価証明書
- その他、遺言者の財産がわかる財産目録
など、上記以外にも必要となる書類は、公証役場に確認して、漏れのないようにしなければなりません。
公正証書遺言の費用は

公証役場へ支払わないといけない費用は、遺産の金額によってことなります。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b10#:~:text=%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%A5%91%E7%B4%84%E5%85%AC%E6%AD%A3%E8%A8%BC%E6%9B%B8,%E5%86%86%E3%81%8C%E5%8A%A0%E7%AE%97%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
公正証書遺言のまとめ

さあ、被相続人、相続人、財産に関する書類もそろい、準備万端、いざ公証人役場へむかいます。
といいたいところですが、書類ができたからと言って、いきなり公証人役場へ向かい遺言書作成にとりかかるようなことはしません。
いきなりアポなしで向かうのではなく、事前に遺言者、または依頼を受けた行政書士が交渉役場とやり取りをし公証人と内容についての打ち合わせをします。内容により、打ち合わせが数回に及ぶこともあります。
FAXでのやりとりや、メールでのやり取りなど公証人とのやり取りの方法は様々。詳しくは公証人役場へお問い合わせください。
やり取りを終えて、「これでいいばっちりできた!」とうところにまで至ってから、公証人役場へ行く日を決めて、証人をこちらで用意してれば証人と公証役場へ行くことになります。
つまり、公証役場へ行く日には、すっかりと下準備が済んでいる状態なんですね。
遺言書の作成が終わると、遺言者、証人、公証人が書面に押印し終了。この時、公証人は遺言書を3通作成します。
1通は原本として公証役場で保管。その他、2通は正本と謄本として遺言者に渡されます。
以上、公正証書遺言についてまとめてみました。
手続きが色々あってめんどくさそうと思っていしまうかもしれませんが、公正証書遺言の効力は絶大です。
転ばぬ先の遺言書として、想いを残してみてはいかがでしょう。
今日は、この辺で。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



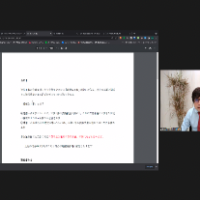


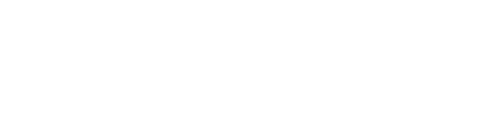
この記事へのコメントはありません。