祭祀承継者とは祭祀承継のまとめ

私には妻と二人の子どもがいます。私が管理してきたお墓や仏壇は誰が受け継ぐんだろう?
祭祀財産は相続財産と区別され、原則、被相続人が指定した者に承継されます。「祭祀承継について」相続専門の行政書士がわかりやすく解説します。
祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)とは

系譜、祭具及び墳墓といった祭祀財産や遺骨を管理し、祖先の祭祀を主宰すべき人のことを指します。
祭祀承継者の決め方は どんな人がなるのか
お墓や仏壇などの資産は、通常、「祭祀財産」とよばれます。
これとは別に、祭祀財産には、他にも系譜(家系図)、位牌、墓地などがあげられます。
祭祀財産は相続財産とは区別されていて、祭祀財産の承継者は祖先の祭祀を主宰すべき者とされています。
承継者になる者の順に
①被相続人が指定した者
②指定者がいないときは慣習に習う
③慣習が不明なときは、家庭裁判所が決める
となります。したがって被相続人が指定しておけば、だれでも祭祀承継者になれるんです。
さらに、祭祀承継は一般の相続とは別なので相続人の中から選ぶ必要もなく、近所の仲のいい人のような、親族でない人でも大丈夫なんです。
家庭裁判所は、被相続人の祖先と深く関係するだけの者より、被相続人と現に密接な関係にあり、被相続人にたいして深い愛情をもって接した者を祭祀承継者に選ぶべきだとしています。
なので、内縁の妻でも祭祀承継者となることもできます。
また、祭祀承継者は、通常一人で行います。
祭祀承継者に選ばれた者が祭祀をしないときは

原則的に、祭祀承継者に選ばれた者は、当然に祭祀承継者となりこれを拒むことはできないとされています。
しかし、祭祀承継者が、祭祀を必ず行わなければならないとう法律上の義務はありません。つまり、たとえ祭祀承継者に選ばれたとしても、祭祀を行うかどうか、祭祀財産をどうするかは、祭祀承継者の意思に任されているのです。
祭祀承継者には財産を多く渡すべきか

祭祀にかかる費用は、祭祀承継者が自ら負担することになります。しかし、よほどの関係でもない限り祭祀にかかる費用を、自腹で捻出するのは現実的に厳しいですよね。
なので、遺言で、被相続人が祭祀承継者を指定し、遺言で特別に遺贈したり、生前に贈与をしておくなどの配慮をするかたが多いです。
被相続人が亡くなっってしまったあとも、相続人が話し合い祭祀承継者に多く財産を分割したり、各相続人が祭祀費用を分担するようにすることもできます。
現実的には、法事などの費用は祭祀承継者の持ち出しになっていることが多いです。自分が亡くなったあと、そのようなことは避けたいと考えるのであれば、遺贈や生前贈与でフォローする対策を考えてみてはいかがでしょうか。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



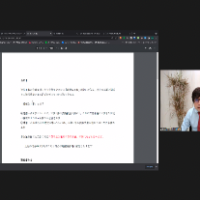

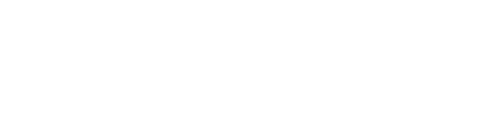
この記事へのコメントはありません。